ギフトマーケティングとは?効果と成功の秘訣を徹底解説
- 株式会社ユニークポイント
- 2025年11月4日
- 読了時間: 20分

▶︎1. ギフトマーケティングとは何か?その重要性と現状
1.1 ギフトマーケティングの定義と位置づけ
「ギフトマーケティング」という言葉、聞いたことはありますか?これは、ギフトを通じてブランドの価値を伝え、顧客との関係を深めるマーケティング手法のことです。近年では、企業がただモノや情報を届けるのではなく、「体験」を届ける時代になりました。その中で、ギフトという“嬉しい気持ちを伴う接点”が注目されています。
たとえば、
イベント来場者に ドリンクチケット や スイーツ引換券 を配布
紹介キャンペーンで 紹介者・被紹介者双方に電子ギフト を配布
定期購入者に 季節限定ギフト(コーヒー豆・バスソルトなど) を同封
ギフトを介すると、広告や販促が「一方的に売り込む」ものではなく、「もらって嬉しい体験」になり、心理的ハードルが下がるため、自然にブランドへの好感や信頼が生まれます。
また、ギフトマーケティングは、単なる販促活動にとどまりません。企業の認知拡大や顧客ロイヤリティ向上、さらにはデータ収集までを担う重要な役割を果たします。
具体的には、
SNSでのシェアや口コミが発生しやすい
ギフト経由で新規顧客にリーチできる
贈り手と受け取り手、双方にブランド体験が残る
といった効果が期待できます。
こうした点から、ギフトマーケティングは「顧客と企業をつなぐブランディング戦略」として、多くの業界で導入が進んでいます。
1.2 ギフトマーケティングが注目される背景(市場・文化の変化)
ここ数年、ギフトマーケティングが一気に注目を集めています。その背景には、「贈り方」や「受け取り方」に対する人々の価値観の変化があります。
まず、生活スタイルのデジタル化が進み、オンライン上で気軽にギフトを贈り合う文化が広がりました。誕生日や記念日だけでなく、「ちょっとしたお礼」や「日常のねぎらい」など、贈るシーンが多様化しているのが特徴です。
たとえば、SNSやチャットで手軽に送れるデジタルギフト。忙しくてもすぐ贈れるため、Z世代を中心に利用が増えています。
一方で、企業のマーケティング活動にも大きな変化が起きています。従来の広告では、「見てもらえるかどうか」が成果を左右していました。しかし、広告があふれる時代において、ただ表示されるだけでは印象に残りません。そこで注目されたのが、「確実に届く」「ポジティブに受け取られる」ギフトを使ったアプローチです。
さらに、データ保護の観点から、企業が顧客の購買データを自由に活用しにくくなったことも影響しています。ギフトマーケティングは、ギフトの受け取りやアンケートを通して、消費者が自ら提供する「ゼロパーティデータ」を得られる手法としても注目されています。これにより、よりリアルで信頼性のある顧客理解が可能になります。
このように、
贈り方の多様化(デジタルギフト文化の拡大)
広告への信頼性低下(“確実に届く”手段の重要性)
データ活用の変化(ゼロパーティデータの価値上昇)
という3つの変化が、ギフトマーケティングの成長を後押ししています。
また、コロナ禍以降の「つながりを大切にしたい」という意識の高まりも無視できません。ギフトは単なるモノのやり取りではなく、気持ちを伝えるコミュニケーション手段として再評価されています。企業がその流れを取り入れ、ブランドの信頼を築く方法としてギフトマーケティングを活用するケースが増えているのです。ギフトマーケティングは、時代の変化に応じて“人とのつながり”を再定義するマーケティング手法といえます。
▶︎2. ギフトマーケティングで得られる3つの主要効果
ギフトマーケティングを導入することで、企業はどんな成果を得られるのでしょうか。ここでは、特に重要な3つの効果に分けて解説します。
2.1 認知拡大とブランドロイヤリティを生むギフトマーケティング
まずひとつ目の効果は「ブランド認知と好感度の向上」です。広告が届いても、興味を持ってもらえなければ意味がありません。ギフトを活用すると、受け取る側に“嬉しい驚き”が生まれ、その瞬間にブランドへの印象が強く残ります。たとえば、企業からもらったギフトカードやオリジナルグッズをきっかけに、「どんな会社だろう?」と興味を持つ人は少なくありません。
また、ギフトを通じたポジティブな体験は、SNSでのシェアや口コミを自然に誘発します。特に20〜40代の層では、「もらった」体験を発信する傾向が強く、結果的に広告効果が拡散します。
ここでのポイントは、「ギフトを通じてブランドのストーリーを伝える」ことです。単なるプレゼントではなく、“企業の想いを形にした贈り物”として受け取られるよう工夫することで、記憶に残るブランド体験を生み出せます。
ギフトマーケティングは、広告では伝えきれない“ブランドの温度”を届ける最も効果的な手段です。
2.2 購買意欲・リピート率を向上させるギフトマーケティング
2つ目の効果は、「購買意欲やリピート率の向上」です。多くの人は「ギフトをもらう=特別扱いされている」と感じます。その心理が購買行動にプラスに働きます。
ギフトマーケティングでは、
新規顧客に体験のきっかけを与える
既存顧客に感謝の気持ちを伝える
購入後のフォローとして特典を贈る
などの施策が有効です。
特に「購入 → ギフト → 再購入」という流れを設計すると、自然にリピート率が高まります。ギフトを通じて“記憶に残るブランド”を築くことで、次の購買時に思い出してもらいやすくなるからです。
さらに、ギフトには“行動のきっかけを作る力”があります。「ギフトを使ってみよう」「ポイントを活用しよう」といった行動が起こりやすく、結果として購買数が増えます。ある調査では、ギフト施策を導入した企業の約6割が、施策後3ヶ月以内に売上が上昇したと報告しています。
ただし注意したいのは、ギフトの内容やタイミングが合っていないと逆効果になりやすい点です。
たとえば、
ターゲットの趣味や価値観に合わないギフト
ギフト送付のタイミングが遅く、感情の熱が冷めてしまう
内容が安価すぎてブランドイメージを損なう
といったケースは要注意です。
これらを防ぐには、顧客データを分析し、「どの層に」「どんなタイミングで」「どんな内容を」贈るかを設計することが欠かせません。ギフトマーケティングは、“もう一度買いたくなる理由”を自然に作る仕組みです。
2.3 ゼロパーティデータ取得などできるギフトマーケティングの副次効果
3つ目の効果は、「データの取得と分析に活用できる点」です。従来の広告では、クリック数や閲覧数などの“間接的な反応”しかわかりませんでした。しかしギフトマーケティングでは、受け取りやアンケート回答を通じて、顧客の本音データ(ゼロパーティデータ)を取得できます。
ゼロパーティデータとは、顧客が自ら進んで提供する情報のことです。たとえば、「どんな理由で選んだか」「どんなシーンで使いたいか」といった回答から、購買意欲や価値観を直接把握できます。これは単なる数値データよりもはるかに価値が高く、次のマーケティング施策や商品改善にそのまま活かせます。また、ギフトというインセンティブがあることで、アンケートの回答率が高く、内容も丁寧になりやすいという特徴があります。
多くの企業がこのデータをもとに、
商品企画の方向性を調整する
ターゲット層ごとの反応を比較分析する
ROI(投資対効果)を可視化する
といった活用を進めています。
データ収集というと難しく感じるかもしれませんが、ギフトを通じて“自然に”データが集まるのがこの手法の強みです。消費者も「もらったお礼に答える」という感覚で協力してくれるため、双方にとって心地よい関係を築けます。ギフトマーケティングは、売上だけでなく“信頼できる顧客データ”という資産を育てる仕組みでもあります。
これら3つの効果を組み合わせることで、ギフトマーケティングは単なる販促ではなく、ブランド戦略の中心的役割を担うようになります。 “認知・購買・データ”のすべてをつなぐのが、現代のギフトマーケティングの本質です。
▶︎3. ギフトマーケティングを成功に導く5つの戦略
ギフトマーケティングは、やみくもに贈ればいいというものではありません。どんなターゲットに、どんなタイミングで、どんな価値を届けるかを設計してこそ、真の効果が発揮されます。ここでは成功企業の傾向をもとに、5つの実践戦略を紹介します。
3.1 ターゲットを明確にするギフトマーケティング戦略
まず最も重要なのが、「誰に贈るのか」を明確にすることです。ターゲットが曖昧なままギフトを配ってしまうと、コストばかりかかって成果が出にくくなります。
ギフトマーケティングでは、以下のようにターゲットを細かく設定すると効果的です。
年齢・性別・職業などの基本属性
購買履歴や興味関心(どんな商品を見ているか)
ブランドとの関係性(新規/既存/休眠顧客)
たとえば、新規顧客には「お試しきっかけ」を贈り、既存顧客には「感謝の気持ち」を伝える。このように目的別に分けるだけでも、反応率が大きく変わります。
さらに、ギフトの内容やデザインもターゲットの嗜好に合わせることで、“自分のためのプレゼント”として感じてもらえます。結果として、ブランドへの愛着が高まり、リピート購入につながります。
3.2 季節・イベントに合わせたギフトマーケティング戦略
次に効果的なのが、「季節やイベントを活用する」戦略です。ギフトはもともと“タイミング”が重要な文化的要素を持っています。
たとえば、
春:新生活応援ギフト
夏:キャンペーン特典としての電子ギフト
年末:感謝を伝えるノベルティギフト
このように時期やシーンを意識してギフトを設計すると、受け取る人の心理に自然に響きます。
季節感を活かすことで、企業のメッセージも柔らかく伝わります。「お中元」や「年末のご挨拶」など、日本独自の文化を取り入れたキャンペーンは特に好感度が高い傾向です。
ただし、配布の時期がずれると印象が弱まったり、在庫や配送の準備が間に合わず混乱する可能性があります。こうしたミスを防ぐには、キャンペーンの1〜2か月前から準備を始めるのが理想です。季節感を意識したギフトマーケティングは、“心に残るきっかけ”を自然に作り出します。
3.3 受け取り率を上げる「手渡し/デジタルギフト」活用戦略
ギフトマーケティングの効果を最大化するためには、「確実に届く仕組み」が欠かせません。その手段として注目されているのが、手渡し型とデジタル型のハイブリッド活用です。
手渡し型は、直接的なコミュニケーションを生みやすい点が魅力です。イベント会場や店舗で配布すれば、相手の反応をその場で得られます。一方、デジタルギフトは場所や時間に縛られず、メールやSNSで即時配布できるのが利点です。
理想は、この2つを組み合わせること。たとえば、イベントでギフトカードを手渡しし、その後フォローとしてデジタルギフトを送る。これにより、「受け取り忘れ」を防ぎつつ、ブランドとの接点を2度生み出せます。
また、受け取り率を上げるためには、“ちょっと嬉しい”金額設定もポイントです。高額すぎると構えられ、低すぎると印象が薄くなるため、500円〜1000円程度のギフトが最も反応が良いとされています。
3.4 ソーシャルで拡散を狙うギフトマーケティング戦略
SNS時代において、ギフトは話題を生むコンテンツとしても機能します。「もらって嬉しかった」「おしゃれなデザインだった」などの投稿は、自然な形で拡散効果を生み出します。
ギフトマーケティングでは、次のような工夫が拡散力を高めます。
パッケージやカードのデザインに“共有したくなる要素”を入れる
SNS投稿キャンペーンを同時開催する
受け取り時の体験を動画・写真で残せる仕組みを用意する
たとえば、「ギフトを開封する瞬間」をシェアできる仕掛けを用意すると、自然に口コミが広がります。このようなSNS連動のギフト施策は、広告費をかけずに認知を広げる手段として注目されています。
ただし、「シェアしてほしい」と一方的に求めすぎると逆効果です。自然な流れで「シェアしたくなる」体験を作ることが大切です。
3.5 データ活用&改善につなげるギフトマーケティング戦略
最後の戦略は、「データを活用し、施策を改善していくこと」です。ギフトマーケティングは“贈って終わり”ではありません。むしろ、ギフトの受け取り後に得られるデータこそが最も重要です。
ギフト配布後に以下の情報を収集すると、次の施策が格段に改善されます。
ギフトの受け取り率
回答アンケートの傾向(性別・年齢・好みなど)
SNS投稿や口コミの反応量
再購入・サイト再訪の動向
これらを分析し、ターゲットや配布タイミングを調整していくことで、施策のROIがどんどん上がっていきます。
よくある失敗は、「配布して満足してしまう」ことです。データの検証を行わないと、せっかくの成果が見えないまま終わってしまいます。配布数や反応率を定期的に可視化し、PDCAを回す仕組みを作ることが大切です。
これら5つの戦略をバランスよく取り入れることで、ギフトマーケティングは単なる一過性の施策ではなく、ブランドの「資産づくり」へと変わります。ターゲット設定、季節感、受け取り率、拡散、データ活用。この5つが噛み合ったとき、ギフトマーケティングは最も強力な顧客接点になります。
▶︎4. ギフトマーケティングの失敗例と注意点
ギフトマーケティングは、正しく運用すれば非常に高い効果を発揮します。しかし、準備や設計を誤ると「思ったほど成果が出なかった」と感じるケースも少なくありません。ここでは、よくある3つの失敗例と、それを防ぐための具体的なポイントを解説します。
4.1 失敗例①:ターゲットが曖昧なまま実施したギフトマーケティング
最も多い失敗は、「誰に向けたギフトなのか」が不明確なまま実施してしまうケースです。ギフトを配布しても、興味のない層に届いてしまえば効果は半減します。
たとえば、たとえば、ビジネスパーソン向けのイベントで学生が喜ぶグッズを配っても響きませんし、逆に忙しい社会人に実用的な電子ギフトを贈れば反応はぐっと高まります。ギフトの価値を感じるかどうかは、ターゲットの状況によって全く違うからです。
この失敗を防ぐためには、以下のような手順で「ターゲット明確化」を行うことが大切です。
顧客データから反応の高い層を抽出する
購買目的や使用シーンを想定してメッセージを作る
ギフトの内容をターゲットに合わせて最適化する
特に重要なのは、“誰に何を贈るのか”を明確にする設計段階です。ここを曖昧にすると、せっかくのギフトが「ただのばらまき」になってしまいます。
4.2 失敗例②:ギフトの価値設計を軽視したギフトマーケティング
2つ目の失敗は、ギフトそのものの「価値設計」を軽視してしまうことです。ギフトは単なるモノではなく、「贈る側の気持ち」や「ブランドの印象」を映す鏡です。
ありがちなミスとしては、 ギフトが安価すぎて印象に残らなかったり、逆に高価すぎて受け取る側が気後れするというケースがあります。
たとえば、若年層向けブランドが高級路線のギフトを贈ると「自分向けじゃない」と感じられ、心理的距離が生まれます。一方で、ブランドの世界観に合ったデザインや用途のギフトであれば、「この企業、センスがいいな」と好印象が残ります。
理想的なギフトは、“受け取ってすぐに嬉しく、長く印象が続くもの”。そのためには、「受け取った瞬間の喜び」と「使うときの便利さ」の両方を意識することが大切です。
4.3 失敗例③:フォローアップ体制が無かったギフトマーケティング
3つ目の失敗は、「ギフトを配って終わり」になってしまうケースです。実施後のフォローやデータ分析が行われないと、せっかくの成果が見えず、次の施策に活かせません。ギフトマーケティングは、配布後のデータ収集が非常に重要です。
たとえば、
どの層が最も反応したか
ギフト受け取り後に購買行動があったか
SNSでの拡散や口コミがどの程度発生したか
といった情報を追うことで、施策の効果を定量的に把握できます。
さらに、アンケートを活用すれば「なぜ反応したのか」「どんな気持ちで受け取ったのか」という定性的データも取得できます。これらのデータを蓄積し、次の施策で改善を重ねることで、広告費のROI(投資対効果)を大幅に向上させることができます。
データを取らないまま終えてしまうのは、言わば“勘に頼ったマーケティング”。最初は小規模でも構わないので、数値を追いかける体制を整えることが大切です。
4.4 各失敗に対する具体的な解決策
ここまでの失敗例を踏まえると、次のような解決策を押さえておくと安心です。
ターゲット明確化:配布前に顧客を属性・興味別に分類する
価値設計の最適化:ブランドイメージと調和するギフトを選ぶ
データ活用の仕組み化:受け取り率・反応率を定期的に計測する
長期運用視点:1回のキャンペーンではなく、継続的に改善していく
また、社内での情報共有も非常に大事です。マーケティング担当だけでなく、営業・開発・カスタマーサポートまで巻き込むと、施策全体の一貫性が生まれます。
さらに、ギフトマーケティングは“顧客との関係を育てる長期戦”です。一度で完璧を目指すよりも、毎回の施策から得た気づきを積み重ねていくことが、最終的な成功につながります。
▶︎5. 確実に届くギフトマーケティングなら「ユニーポ」のご紹介
ギフトマーケティングの価値を最大限に発揮するためには、「確実に届く」仕組みが不可欠です。どんなに魅力的なギフトでも、相手に届かなければ意味がありません。
その課題を根本から解決するのが、Amazonギフトカードを活用した広告モデル「ユニーポ」です。
ユニーポは、「届くかわからない広告」を「確実に届く広告」に変える新しいマーケティング手法を提供しています。金銭的価値のあるギフトを使うことで受け取り率を100%に近づけ、広告を“捨てられない”ものに変えます。
5.1 ユニーポが実現する“確実に届く”ギフトマーケティングモデル
ユニーポの最大の特徴は、「確実に届く」ことが保証される広告モデルである点です。
従来のWeb広告やチラシでは、配信や配布をしても実際に見てもらえるかどうかは分かりません。しかしユニーポでは、広告デザインを施したAmazonギフトカードをターゲット顧客に直接手渡すため、到達率は100%です。
この仕組みにより、配布枚数=広告の到達数という明確な指標が生まれます。無駄な広告費が発生せず、「確実な投資」としての広告運用が可能になります。また、ギフトカードには金銭的価値があるため、受け取った人が破棄することはほとんどありません。財布やデスクにしばらく保管されるため、ブランドロゴやメッセージが長期間視界に入り続けます。
これにより、単発的な接触ではなく、継続的な認知効果が期待できます。ユニーポは、従来の「届くかわからない広告」を“確実に届くギフトマーケティング”へと進化させた仕組みです。
5.2 広告主・消費者・加盟店それぞれにもたらすギフトマーケティングのメリット
ユニーポの仕組みは、広告主・消費者・加盟店の三者すべてにメリットがあります。それぞれの立場から見てどんな利点があるのかを整理してみましょう。
■ 広告主のメリット
ターゲット顧客に確実にリーチできる
ギフトカードの配布枚数がそのまま効果測定に直結する
アンケートを通じてリアルな消費者データを取得できる
広告主にとって最大の魅力は、「広告の不確実性がゼロになる」ことです。どれだけの人に届いたか、どんな反応があったかが数値で可視化されるため、投資判断が明確になります。
■ 消費者のメリット
広告を“押し付けられるもの”ではなく“嬉しい贈り物”として受け取れる
金銭的価値があるため受け取り率が高い
ギフトを通じてブランドに対してポジティブな印象を持てる
従来の広告は「興味がないものが一方的に届く」ものでしたが、ユニーポの広告は「ちょっと嬉しい体験」として受け入れられます。この体験が、企業への信頼や好感につながります。
■ 加盟店(配布店舗)のメリット
ギフトカードの配布が新たな集客のきっかけになる
顧客との会話が生まれ、リピートにつながる
店舗のイメージアップや顧客接点の強化ができる
加盟店にとっても、ギフト配布は“来店理由”をつくる絶好のチャンスです。実際、ギフトカードをきっかけに店舗を訪れた顧客が、その後定期的に来店する傾向も見られます。ユニーポは、広告主・消費者・店舗のすべてに“嬉しい循環”を生み出すギフトマーケティングモデルです。
5.3 導入の流れと活用のポイント
ユニーポの導入はシンプルで、次の3ステップで始められます。
目的設定とターゲット選定 広告の目的(認知・集客・リピート促進など)を明確にし、配布ターゲットを設定します。
デザイン制作とギフトカード発行 ブランドイメージに合わせた広告デザインを作成。Amazonギフトカードと組み合わせて印刷・発行します。
配布・データ収集・分析 ターゲット顧客に手渡しし、アンケートや行動データを取得。次回施策への改善に活かします。
導入後は、ギフト配布後のデータをもとに、広告の効果を定期的に分析します。特に、「受け取り率」「アンケート回答率」「ブランド認知度」などをKPIとして設定すると、成果を定量的に評価できます。
また、ユニーポではAmazonギフトカードの公式ベンダーとしての実績があり、信頼性・安全性の面でも安心して導入できます。デザイン・印刷・配布・分析までをワンストップでサポートするため、初めてギフトマーケティングに挑戦する企業にも最適です。ユニーポを活用すれば、“広告をコストではなく投資に変える”ギフトマーケティングが実現します。
ユニーポは、広告主が抱える「広告が届かない」「効果が見えない」といった悩みを根本から解決します。ギフトの力を活かした新しいマーケティングで、確実に届け、確実に記憶に残す。それが、ユニーポが提案する次世代のギフトマーケティングです。
▶︎6. ギフトマーケティングの未来と導入ステップまとめ
ギフトマーケティングは、今後さらに進化を続ける分野です。単なる“販促手法”ではなく、顧客との信頼関係を築くためのブランド戦略として、多くの企業が注目しています。ここでは、その未来の方向性と、導入に向けて実践すべきステップを整理します。
6.1 ギフトマーケティングが向かう未来トレンド
これからのギフトマーケティングは、3つの方向へと進化していくと考えられます。
① パーソナライズの高度化
AIやデータ分析の進化により、顧客一人ひとりに合わせたギフト内容を設計できるようになります。たとえば、過去の購買履歴やアンケート回答をもとに、「その人が本当に欲しいもの」を贈る仕組みが可能になります。
② オンラインとオフラインの融合
デジタルギフトの普及により、オンライン上での贈り物が当たり前になりました。今後は、リアルイベントや店舗での配布と組み合わせる「OMO型ギフトマーケティング」が主流になるでしょう。
③ データ資産としてのマーケティング活用
ギフト施策によって得られるゼロパーティデータは、企業の貴重な資産です。将来的には、このデータをもとに、広告配信・商品開発・ブランド設計がすべて連動していく時代になります。消費者が“受け取る側”から“共にブランドを作る側”になる未来が見え始めています。
6.2 今すぐ始めるギフトマーケティング導入ステップ
ギフトマーケティングをこれから導入する場合、以下の5ステップで進めるとスムーズです。
目的を明確にする まず「認知拡大」「購買促進」「リピート向上」など、目的を具体的に設定します。
ターゲットを定義する 誰に贈るのか、どんな層に反応してほしいのかを明確にしましょう。
ギフトの内容・形式を決める 金銭的価値・デザイン・使いやすさをバランスよく設計することがポイントです。
配布方法を選ぶ(手渡し or デジタル) ターゲットの生活スタイルに合わせて最適な形式を選びましょう。
データを収集し、次の施策に活かす アンケートやアクセス解析を通じて得た情報を分析し、改善を続けます。
この5ステップを繰り返すことで、広告施策が「一度きりの配布」から「継続的に成長する仕組み」へと変化します。ギフトマーケティングは、導入すること自体よりも、改善し続けることが最大の成功要因です。
6.3 本記事のまとめ
ここまで、ギフトマーケティングの定義から実践方法、そして未来の展望までを解説しました。最後にポイントを整理します。
ギフトマーケティングは「贈る体験」を通じてブランド好感度を高める手法
認知拡大・購買促進・データ収集の3つの効果がある
成功の鍵は、ターゲット設定・タイミング・価値設計・データ活用の4要素
ユニーポのように“確実に届く”仕組みを活用することで、効果はさらに高まる
今後はAIやデジタル技術により、よりパーソナルなギフトマーケティングへ進化していく
ギフトは、モノではなく「感情を届ける」ツールです。企業がその力を正しく使えば、広告は単なる情報発信ではなく、顧客の心に残る“贈り物”へと変わります。ギフトマーケティングは、これからの時代における“最も人間的なマーケティング手法”です。





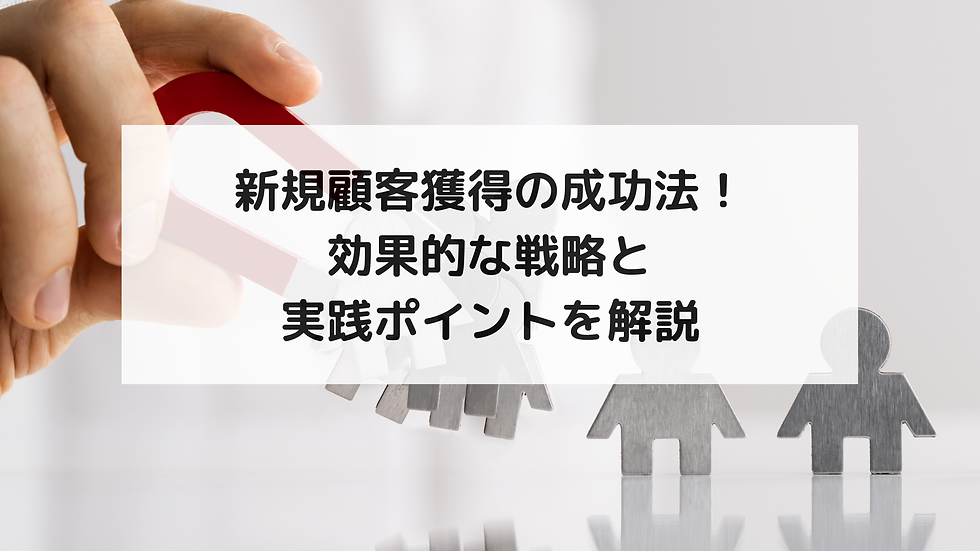
コメント